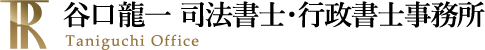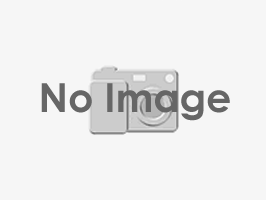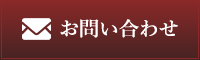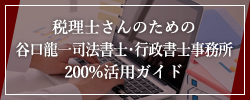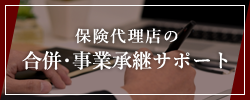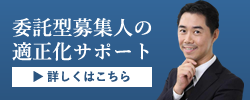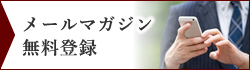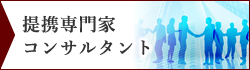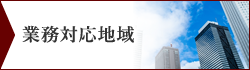コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
一部の相続人には財産を残さない旨の遺言の場合には遺留分に注意
2020/03/29自筆証書遺言でも財産目録は印刷したものや登記簿謄本でも大丈夫になりました
2020/03/28家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧める理由
2020/03/27相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。
あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。
しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。
夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり
上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると相続人間で合意されている。
もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。
家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。
さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。
そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の合計5500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。
相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。
公正証書遺言の保管期間は?
2020/03/26自筆証書遺言の法務局保管制度の手数料が発表されました
2020/03/24「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布されました。
比較的低額ですので、銀行の貸金庫よりも安上がりですね。
遺言書の保管の申請等の手数料
1.遺言書の保管 1件につき3,900円
2.遺言書の閲覧 1回につき1,700円
3.遺言書情報証明書の交付 1通につき1,400円
4.遺言書保管事実証明書の交付 1通につき800円
遺言書保管ファイルの記録の閲覧等の手数料
1.遺言書保管ファイルに記録された事項の閲覧 1回につき1,400円
2.申請書等又は撤回書等の閲覧 1回につき1,700円
遺言に書く不動産の表記は登記簿謄本の通りに正確に
2020/03/23住所で表記する場合の問題点
固定資産税評価証明書で表記する場合の問題点
自筆証書遺言に押すハンコは実印でないといけない?
2020/03/22相続で遺産が不動産だけで分け方に困ったら
2020/03/21子供に財産を遺すとの遺言を作るときに、子供が先に亡くなった場合も考えてますか?
2020/03/21夫婦で遺言を作るときは相手が先に亡くなった場合も考えてますか?
2020/03/20
- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740