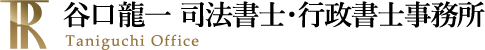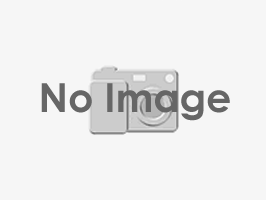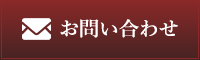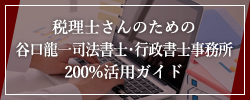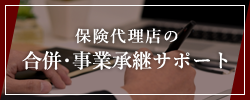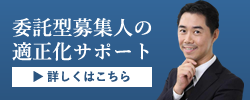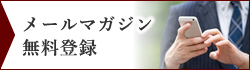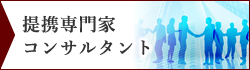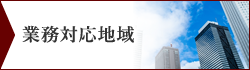- ホーム
- コラム
コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
古物商の許可について
2012/08/07今回は、古物商の許可について述べさせて頂きたいと思います。
まず、古物についてですが、古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの(例えば、誰かに戴いたが、一度も使用せずに自宅に保管している贈答品などです)又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。これらの古物を買い取って、お店等で販売する場合は、古物商の許可が必要になります。
逆に自分で使用する為に購入した物をオークションなどでネット販売する場合などは、古物商の許可は、不要です。
また、許可を取得する際の要件としては、次のいずれにも該当しないことです。
①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
③住居の定まらない者
④古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
⑤営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商の許可申請を提出する際の注意点としては、申請の添付書類として、法人の場合は、会社の登記謄本が必要ですが、謄本の目的の欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載がなければ、許可が取れない都道府県と、記載がない場合は、後日変更すれば、申請時には、記載がなくても取れる都道府県があるので、営業所を設けようとする場所を管轄する警察署に確認が必要です。
また、許可は、公安委員会ごとに受ける必要があるので、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けようとする場合は、それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要です。
更に古物商の許可を取得した後、次のいづれかに該当した場合、営業停止や許可取消処分となりますので、注意が必要です。
①古物商の許可を受けたのに6ヶ月過ぎても営業を始めない
②営業を開始したものの、6ヶ月以上も休業が続いている
③古物商の商人が、3ヶ月以上も所在不明になっている
以上、古物商許可を取得する際の注意点を中心に述べさせて頂きました。
古物商の許可申請は、要件と書類さえ揃っていれば、申請書の作成自体は、難しくは、ございません。ご不明な点がございましたら、いつでもご相談下さいませ。
会社設立の注意点(3) 本店所在地
2012/08/07商業登記を担当している出口です。
株式会社設立において、賃貸物件を本店として登記する場合は、予め貸主の了解を得ておくことをおすすめします。また、その際はいつから登記を置いてもよいか確認しておきましょう。
特に、会社の設立登記後に賃貸契約を結ばれる場合は注意が必要です。
なぜなら、登記をする時にはまだ借りていない物件を、了解もなく会社の本店として登記すると、他人の所有物件に勝手に登記を置くような形になってしまうからです。貸主によっては気分を害され、契約締結を拒否されるなどのトラブルになることもあります。
賃貸契約を結ぶ前には登記を置かないで欲しいと言われた場合は、賃貸契約を結ぶ時期又は設立登記の申請時期を再検討する必要が出てきますので、早めに確認しておく方がよいでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
建設業許可について(2)
2012/08/07前回は、許可の概要について述べさせて頂きましたので、今回は、建設業許可の詳しい許可要件について述べさせて頂きます。
まず許可を取得するには、経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者を置く必要があります。
経営業務の管理責任者に該当する要件としては、法人の場合は、常勤の役員、個人の場合は、本人又は支配人が、下記のいずれかに該当することが必要です。
○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験があること。
※補佐とは、法人の場合は、役員に次ぐ職務上の地位、個人の場合は、個人に次ぐ職務上の地位にあった人のことをいいます。
営業所の専任技術者に該当する要件としては、一定の国家資格を持っていることや、10年以上の実務経験を有していることなどがあります。
又、許可の申請書を提出する際には、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に該当する旨を証明する書類が必要になります。
経営業務の管理責任者の場合は、法人の場合は、会社の謄本、個人の場合は、確定申告書が証明書類となり、それぞれ経験年数分必要です。
営業所の専任技術者の場合は、過去の工事の契約書又は注文書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)と請求書と入金を確認できる通帳の写し等が必要となります。
その外にも、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者ともに、健康保険被保険者証等、常勤を証明する書類も必要となります。
上記の書類は、建設業許可取得の核となる部分であり、上記の書類が揃わない為、許可が取得できないケースもございます。
過去の注文書が残っていない場合、若しくは、口頭で注文を請けている為、注文請書を出していない業者の方も多いと思います。その場合は、元請の会社に何か発注したことの証明になる書類が残っていないか、また残っていない場合は、注文したことの証明として工期、工事内容、金額等を記載した発注証明書を元請の会社に出して貰い、注文書の代わりにすることが、考えられます。
ですが、その場合でも各都道府県・土木事務所によって手続きに違いがあり、発注証明書では不十分として、追加でその他の書類を求められる可能性もあります。
以上が、許可取得の要件です。これから許可を取得される業者の方は、注文を請ける際に、注文請書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)を出したり、契約書を取り交わすようにしておくと、許可取得を申請する際にも、スムーズに手続きが進められると思います。
建設業については、こちらをご覧下さい。
株式会社設立の注意点(2)役員構成
2012/08/07商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
お客様から「株式会社を設立したい。役員は身内のみで4名にしたい。」と相談があった場合、どのような役員構成が考えられるでしょうか?
一般的には下記のような役員構成で検討することが多いかと思います。
① 取締役会は置かず、取締役4名 監査役は置かない
② 取締役会は置かず、取締役3名 監査役1名
③ 取締役会を置き、取締役3名 監査役1名
当事務所では、①か②をお薦めしています。
なぜなら、取締役会を置いた場合、最低でも取締役3名以上、監査役1名以上が必要と定められているため、常に役員を4名以上置く必要があるからです。
設立当初は問題がなくても、時間が経ち、役員が辞めたり、亡くなられたりした場合、新しく役員になってもらう方を探すのが難しいこともあります。
もちろん、③の場合でも取締役会を廃止すれば、4名以上置く必要は無くなりますが、役員の辞任等と共にに登記する場合、登録免許税が最低でも4万円必要となります。株式の譲渡制限の承認機関を「取締役会」にしている場合は、その変更も必要となるため、更に3万円必要となります。
その点、①②の取締役会を置かない場合は、役員変更の登録免許税1万円で足りることになります。
大きな会社では、株主総会を開かずに取締役会で決議することができるメリットは大きいかと思いますが、中小企業で株主が少数の場合、取締役会を置くメリットは少ないのではないでしょうか。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
株式会社設立の注意点(1)類似商号・会社名
2012/08/07代表の谷口です。
旧商法19条では、同一市町村で類似した会社名で同一の目的(事業内容)の会社設立は禁止されていました。
しかし、現在の企業活動の広がりや類似商号に該当するかどうかの判断が難しいなどの理由により、類似商号禁止規定は廃止されました。
ただ、同一本店で同一会社名が複数存在するのは適当ではないため、目的(事業内容)が異なっていたとしても、同一本店・同一商号の登記は出来ません。(商業登記法第27条)
このように類似商号規制は廃止されましたが、不正競争防止法による「不正競争」に当たる行為の規制は今までと同じくあります。
したがって今後も、場合によっては似た会社名の会社がないかの調査はする方がよいでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
専門家を紹介
2012/08/07代表の谷口です。
当事務所には、登記、相続、借金問題、許認可、税金、年金、従業員とのトラブル、特許等いろいろな相談があります。
裁判なら弁護士さん、税金のことなら税理士さんというイメージを持ってらっしゃる方は多いと思いますが、それ以外のこととなると「誰に相談すればいいのか分からなかったので、取りあえず相談してみた」という方が多いです。
当事務所で対応できない問題もあり、
裁判のことは弁護士さんを紹介します。
http://www.nichibenren.or.jp/
社会保険や年金、就業規則、従業員さんの問題は社会保険労務士さんを紹介します。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
税金のことは税理士さんを紹介します。
http://www.nichizeiren.or.jp/
特許のことは弁理士さんを紹介します。
http://www.jpaa.or.jp/
監査のことは公認会計士さんを紹介します。
http://www.hp.jicpa.or.jp/
境界のことは土地家屋調査士さんを紹介します。
http://www.chosashi.or.jp/
不動産の鑑定のことは不動産鑑定士さんを紹介します。
建築のことは建築士さんを紹介します。
経営のことは中小企業診断士さんを紹介します。
当事務所は、上記の外にも不動産業者さん、ホームページ制作会社さん、保険代理店さんなど幅広い人的ネットワークがあるので、どこに相談していいか分からないときは、とりあえず相談してみてください。
建設業許可(1)許可の概要
2012/08/07許認可には様々な種類がありますが、最初に建設業の許可について述べさせて頂きたいと思います。
まず、建設業許可の概要ですが、建設業許可には、28種類の工事業種があり、各工事を営む場合には、建設業法の規定により、軽微な工事のみを請負う業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可を受ける必要のない軽微な工事とは、次のような工事を指します。
○建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込)に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
○建築一式工事以外の場合・・・工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込)に満たない工事
建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、大臣許可とは主な営業所以外の営業所が、他府県にある業者が取得します。知事許可は、1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業している業者が取得します。
又、よくある質問として、例えば京都府で許可を取得した場合、京都府内でしか工事はできないのかとの質問がございますが、京都府以外であっても工事はできます。
さらに特定建設業許可と一般建設業許可とに分れ、特定建設業許可とは、元請工事を下請業者に発注して工事する場合に、その下請代金の額が4,500万円以上(消費税込)になる場合、特定建設業の許可を取得しなければなりません。(建築一式工事以外は3,000万円以上(消費税込))
建設業許可の有効期間は、許可日より5年を経過する日の前日迄です。
引き続き、建設業を営む場合は、期間が満了する30日前迄に更新の手続きを取ることになります。以上が、概要となります。
次回は、詳しい取得要件についてお話させて頂きたいと思います。
建設業についてはこちらをご覧下さい。
相続手続の期間
2012/08/07代表の谷口です。
相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。
相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。
しかし長期間登記手続を放置しておくと、戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる、あるいは相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがあります。
当事務所では、特別な事情がない場合は、1回忌ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。
なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい。

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740