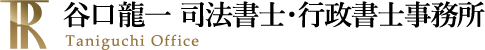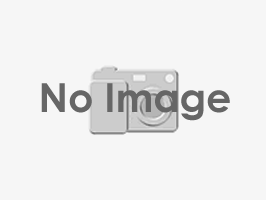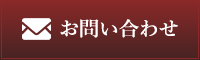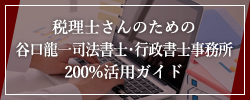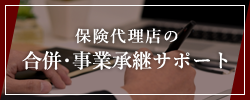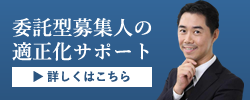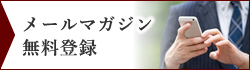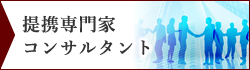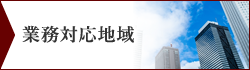- ホーム
- コラム
コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
建設キャリアアップシステムの登録方法(インターネット申請)
2020/02/291、インターネット申請ガイダンスを確認
2、申し込み
3、登録料の支払い
4、確認・審査
5、登録完了
6、建設キャリアアップシステムカードと技能者IDの受領建設キャリアアップシステムに登録するメリット
2020/02/28建設キャリアアップシステムとは
2020/02/27
1.建設キャリアアップシステムとは
建設業が将来にわたって、その重要な役割を果たしていくためには、現場を担う技能労働者(技能者)の高齢化や若者の減少といった構造的な課題への対応を一層推進し、建設業を支える優秀な担い手を確保・育成していく必要があります。
そのためには、個々の技能者が、その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠です。
建設業に従事する技能者は、他の産業従事者と異なり、様々な事業者の現場で経験を積んでいくため、個々の技能者の能力が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が処遇に反映されにくい環境にあります。
こうしたことから、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指す「建設キャリアアップシステム」の構築に向け、官民一体で取り組んでいるところです。
平成31年4月、建設キャリアアップシステムの本格運用が始まりました。
2.建設キャリアアップシステムの概要
○概要
システムの利用に当たり、技能者は、本人情報(住所、氏名等)、社会保険加入状況、建退共手帳の有無、保有資格、研修受講履歴などを登録します。事業者は、商号、所在地、建設業許可情報を登録します。登録により、技能者には、ICカード(キャリアアップカード)が配布されます。
現場を開設した元請事業者は、現場情報(現場名、工事内容等)をシステムに登録し、技能者は現場入場の際、現場に設置されたカードリーダー等でキャリアアップカードを読み取ることで、「誰が」「いつ」「どの現場で」「どのような作業に」従事したのかといった個々の技能者の就業履歴がシステムに蓄積される仕組みとなっています。国土交通省HPより
建設業許可申請に必要な書類 【納税証明書】
2020/02/26建設業許可申請に必要な書類 【確定申告書の控え】
2020/02/25建設業許可には、経営経験があったという条件があります。
具体的には、個人事業主として建設業を5年以上営んでいた、建設業を営んでいた法人で5年以上役員であった等です。この条件に該当していることを証明するためにの一つとして「確定申告書の控え」を提出する必要があります。
個人で建設業許可を持っているが法人化した場合、許可を引き継ぐことはできる?
2020/02/24登記上の本店は自宅の京都だが、実際の事務所は大阪の場合、建設業許可申請はどこにすればいい?
2020/02/23会社設立と建設業許可取得の流れ、期間
2020/02/22会社設立と同時に建設業許可を取りたいとのご依頼があります。
ご相談から許可が出るまでの流れは下記のとおりです。
1.経営業務の管理責任者・専任技術者に関する書類を揃えて頂きます。
↓
2.書類をお預かりしてその書類で許可が受けられるか、検討、場合によっては当事務所が行政庁に相談に行きます。
↓
3.許可申請書内容記載シート等を書いて頂きます。
設立に向けて会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せをします。
↓
4.上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、出資者、取締役の印鑑証明書の取得等をして頂きます。
↓
5.書類に押印して頂く。
↓
6.会社設立申請。
↓
7.会社設立完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却
↓
8.建設業許可の準備をします。各種保険の手続きをして頂くとともに、各種書類を準備して頂きます。
↓
9.当事務所が作成した申請書に捺印して頂きます。
集めて頂いた書類をお預かりします。
↓
10.建設業許可申請。
↓
11.申請が受け付けられましたら、約30日〜40日後に許可が下ります。
ご相談から許可が出るまでの期間は早い場合で3か月程度です。
それ以上に時間がかかる場合があるので、早めに準備されることをお勧めします。
建設業許可の取得の流れ、期間
2020/02/21建設業許可申請に必要な書類 【残高証明書】
2020/02/20建設業許可申請に必要な書類 【被保険者標準報酬決定通知書】
2020/02/19建設業許可申請に必要な書類 【身分証明書】
2020/02/18建設業許可申請に必要な書類 【登記されていないことの証明書】
2020/02/17建設業許可の更新は有効期間の切れる30日前までに
2020/02/16個人で建設業許可を取ったが親が死亡した場合、子供が許可を引き継げる?
2020/02/15建設業許可の事務所は自宅ではダメか?
2020/02/14京都で建設業許可を取っても大阪では工事は出来ない?
2020/02/13株式会社や合同会社などの会社の種類は前がいい?それとも後ろがいい?
2020/02/12
- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740