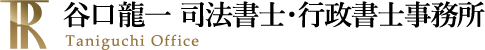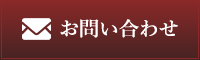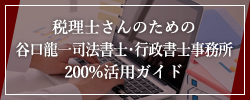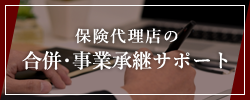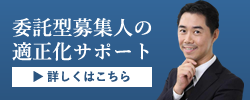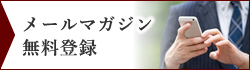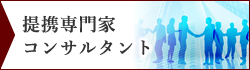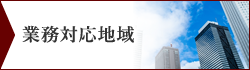- ホーム
- コラム
コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
相続・遺言
遺言で遺すとした財産を使ったり売ってはいけない?
2020/03/19
「遺言で不動産や預金を相続させると書いたら、高齢者施設に入所したりするために不動産を売ったり、預貯金を使ったりできないでしょうか?」とのご相談があります。
もしも、不動産を売ったり、預金を使えないとなると遺言を書くことによって生活がとても制限されてしまうことになるので、大変ですよね。
遺言はあくまで、遺言を書いた人が亡くなった時点で持っている財産をどのように相続させるかというものなので
遺言を書いた時点での財産を必ず残さなければならないことはありません。したがって不動産を売ったり預貯金を使ったりしても問題はありません。
相続・遺言
遺産分割協議書には実印で押印して印鑑証明書は必須?
2020/03/18
遺産分割協議書に実印で押印しなければならなか、また印鑑証明書が必要かは法律で規定はありません。
しかし、認印でいいなら偽造されるおそれもあります。
そこで法務局は通達で遺産分割協議書にもとづいて不動産の名義変更する際には印鑑証明書が必要とされています。
なお有効期限は多くの場合3ヶ月ですがこの場合には有効期限はありません。
また相続による預金の払い戻しや株の名義変更をする銀行や証券会社も印鑑証明書を求めます。
有効期限はそれぞれの銀行や証券会社が社内規定として決めています。
以上のことから、遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書を添えて置くことは法律上必須ではありませんが「事実上」必要です。
なお、法務局や金融機関などを同時に手続きをするなら、印鑑証明書を何通かとっておいたほうが早く手続きを進めていくことができます。
相続・遺言
自筆証書遺言の保管はどうすればいい?
2020/03/18
公正証書遺言であれば原本を公証役場が保管してくれるので安心なのですが、
自筆証書遺言の場合はどのように保管すればいいか、それぞれの方法が一長一短なので難しい問題です。
貸金庫で保管する
安全だが、相続人に貸金庫で保管していることを伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
専門家に保管してもらう
安全だが、遺言を書いた人が亡くなったことが伝わらないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
相続人に保管してもらう
上記の2つと異なり保管している相続人が遺言の存在を知らないということはないが、
保管している相続人が他の相続人に遺言の存在を隠す恐れがある。
遺言を書いた人の自宅で保管する
手続きが簡単だが、相続人に遺言の保管場所を伝えていないと、遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むおそれがある。
公正証書遺言がやはりお勧め
上記の通り、自筆証書遺言では保管場所の問題もあることから、私は公正証書遺言をお勧めしています。
相続・遺言
公正証書遺言を作りたいが証人を頼める人がいないがどうすればいい?
2020/03/17公正証書遺言を作成するには証人2名の立ち合いが必要
証人が2名必要ですが、下記の人は証人となることが出来ません
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人簡単に言うと親族や遺言に関わる人はダメで、中立な立場の第三者でなければいけないという事です。
また、上記以外には証人の資格などは問われませんので、弁護士や司法書士などの専門家でなくても、一般の方でも証人になることが出来ます。
証人になってくれる人がいない場合どうすればいい?
遺言の中身を知られたくないなどの理由から、上記のような人以外に証人を頼める人がいないなどの場合があります。
このような場合には弁護士や司法書士などの専門家に証人になってもらうことがあります。
専門家に公正証書遺言の作成を依頼した場合、通常は専門家が証人になります。
専門家に依頼せずに公正証書遺言を作成した場合は、公証人が紹介してくれることもあります。
相続・遺言
2人まとめて1通の遺言を作れる?
2020/03/16
ご夫婦で相続に関するご相談に来られて「お互いに全財産を相手に残したい。同じ内容なのでまとめて1通の遺言を作れますか?」というご相談があります。
例えば下記のような遺言です。
遺言書
河野太郎と河野花子は死亡したときには、お互いにすべての財産を相続させる。
令和〇年〇月〇日
河野太郎 印
河野花子 印
こういった遺言を共同遺言といいます。
このような共同遺言はは法律関係が複雑になったり、各自が自由に遺言を撤回、変更できなくなって、真意が確保できなくなるなどのおそれがあります。
そこで法律ではこのような共同遺言を禁止しています。
そして、共同遺言は無効となってしまいます。
せっかく作った遺言が無効にならないように共同遺言を作ってしまわないようにご注意ください。
相続・遺言
検認とはなに?
2020/03/15自筆証書遺言は公正証書遺言と異り作成の段階で証人が立ち会ったり、公証人が関与していないので、改ざんや隠匿のおそれがあります。
そこで遺言の改ざん、隠匿などを防ぐため検認の手続きをすることが法律で義務づけられています。
検認の手続きは家庭裁判所が遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認の手続きが終わっていない自筆証書遺言では相続手続きが受け付けられないことがあります。
そして自筆証書遺言の保管者または遺言を発見した相続人は遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
したがって、自筆証書遺言を保管、発見した場合、出来るだけ早く家庭裁判所での検認の手続きをしなければなりません。
相続・遺言
遺言執行者とは何をする人?
2020/03/14
遺言を作成された方がなくられた場合、遺言に基づいて不動産や株の名義変更、預貯金の払い戻しなどの手続きをすることになります。
では、この手続きはだれがするのでしょうか?
公正証書遺言を作った公証役場や自筆証書遺言の検認を受けた家庭裁判所などの公的機関が手続きをしてくれるのでしょうか?
残念ながら、これらの公的機関がこれらの手続きはしれくれません。
手続きをする役所・機関にもよりますが、遺言に遺言執行者を定めていなければ、相続人全員で共同して手続きをしなければならないこともあります。
遺言執行者は相続人に代わって相続手続きをする人です。
相続人が複数いる場合には、手続きをするのが大変になります。
これに対して、遺言に遺言執行者を定めておけば、原則として遺言執行者の一人だけで手続きをすることが出来ます。
また、遺言執行者は弁護士さんや司法書士などの法律専門家でなくても、相続人もなれます。
したがって、相続手続きを簡便に進めるために遺言執行者を遺言で定めることをお勧めしています。
相続・遺言
自筆証書遺言の法務局保管制度
2020/03/13自筆証書遺言の現状、問題点
現在、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失、改ざんのおそれが指摘されていました。
上記のような紛失、改ざんをなくすために、法務局で遺言を保管する制度が作られました。
なお、この制度は2020年(令和2年)7月10日から開始されます。
法務局における遺言の補完制度の概要
・遺言書の原本を法務局が保管し、画像データ化することにより、紛失・改ざんを防ぐ
・家庭裁判所での検認が不要
・遺言を書いた人が死亡したのちに相続人の一人が遺言の証明書を交付を受けるなどした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知することによって、遺言の存在の把握が容易になる
相続・遺言
自筆遺言と公正証書遺言の違い、どちらがお勧め?
2020/03/12「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
一般的に利用されている遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
それぞれにメリット・デメリットがあるのでご自身にあった遺言を選ばれることをお勧めします。
自筆証書遺言
メリット
・作成が簡単
・証人の立ち合いが不要
・作成費用が不要
デメリット
・財産目録以外は手書きでしなければならない
・改ざん、紛失のおそれがある
・家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言
メリット
・全文を手書きできなくても署名だけでもよい
・原本が公証役場で保管されているので、改ざん・紛失のおそれがない
・家庭裁判所での検認が不要
デメリット
・作成に公証人の費用が必要
・証人の立ち合いが必要
どちらがいいの?
ご自身の状況や相続人の状況等にもより一概にどちらがいいとは言いにくいですが、
当事務所としては大事な書類ですので紛失等のおそれのない「公正証書遺言」をお勧めしています。
建設業許可・経営事項審査
経営事項審査の点数アップ【利益剰余金】
2020/03/11利益剰余金
計算式:利益剰余金/1億
高いほどよいことになります。
点数アップの対策
利益(内部留保)を積み上げるしかありません。
ただし、点数に占める割合が少ないので、大企業でなければあまり重視する必要はないでしょう。
- 2021/01
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/04
- 2019/03
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2017/04
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/04
- 2015/03
- 2014/11
- 2014/09
- 2014/07
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/11
- 2013/10
- 2013/09
- 2013/08
- 2013/07
- 2013/06
- 2013/05
- 2013/03
- 2013/01
- 2012/12
- 2012/10
- 2012/08

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740