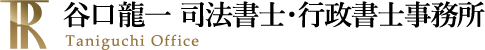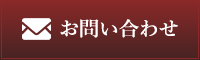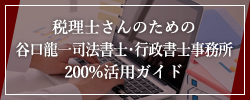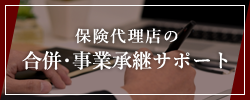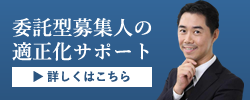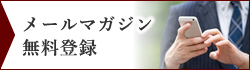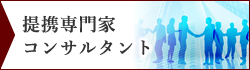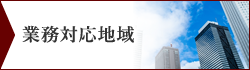- ホーム
- コラム
コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
内容証明郵便
2013/03/01相続と許認可を主に担当しております佐藤です。
契約を解除したい時や、貸付金の支払催促、債権譲渡の通知などの時には、口頭で意思を伝えただけでは証拠が残らず、後々双方で争うことにもなりかねません。そこで、どのような内容を、いつ、誰に郵送したかを、郵便局に証明して貰い、書面で証拠を残す制度が、内容証明です。
内容証明を送るメリットとしては、証拠を残せることや、差出人の真剣さが伝わり、相手方への心理的圧迫効果を期待できることです。
内容証明には、上記のようなメリットもありますが、相手方に誠意が感じられる時や、今後も付き合いのある人、差出人にも非がある場合などの時は、内容証明を出すことによって、相手方の感情を害し、逆に双方の関係性を悪化させてしまい、問題が更にこじれる場合もありますので、内容証明を出す際には、出すべきか、出さないべきか、よく考える必要がございます。
また、内容の書き方についても相手方に心理的圧迫効果を与えたいが為に、脅迫ともとれるような表現であった場合は、脅迫罪や恐喝罪にあたる場合もございますので、書き方についても注意する必要がございます。
成年後見制度
2013/01/28成年後見制度とは、認知証や精神障がい等により判断能力が低下された方がおられる場合、成年後見人を選任し、その方の代わりに、成年後見人が契約を結んだり、預貯金等を管理する制度のことです。
成年後見の申立ては、家庭裁判所に申立てをする必要があり、成年後見人には、下記の成年後見人になれない場合にあたる方以外の方なら誰でも就任することができます。ただし、成年後見人を選任するのは家庭裁判所なので、成年後見人の候補者が、必ず成年後見人に選任されるはと限りません。
[成年後見人になれない場合]
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人(不正な行為等を理由に家庭裁判所から成年後見人(保佐人・補助人)または未成年後見人の地位を解任された者。)
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者
成年後見制度には、不利益な契約を取り消すことができたり、成年後見人に財産を管理して貰えるメリットがありますが、選挙権を失なったり(被保佐人、被補助人の場合は、失いません)、会社の取締役だった方は退任しなければならない(被補助人の場合は退任の必要がありません)等のデメリットがあります。
成年後見制度は、上記のようなメリット・デメリットはありますが、判断能力が低下された方を、法律的に保護できる制度なので、高齢化社会が進むにつれ、これから申立てる方が増えると思われます。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい
本店所在地はどこまで登記すべきか?会社設立の注意点(7)
2013/01/22商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
本店所在地は番地まで記載しなければなりませんが、ビル名やマンション名、部屋番号などは記載しなくても登記することができます。
ビルの一室を借りて本店を置いている場合、設立当初は考えていなくても、後々手狭になり、同じビルで別の部屋に移転するということはそう珍しいことではありません。
この場合、部屋番号まで登記していれば、本店移転登記をしなければなりませんが、番地まで、又はビル名までしか登記していなければ、登録免許税が3万円かかる本店移転登記は不要です。
また、代表者の住所を本店に置かれる場合、会社の登記簿は誰でも見ることのできるものなので、自分の住んでいるマンション名、部屋番号を載せたくないという方もいらっしゃることと思います。
本店所在地と同様に代表者の住所も番地までの記載で構いません。
どちらの場合も気を付けなればならないのは、記載していなくても郵便物が届くかどうかです。
通常、番地まで記載があればビルやマンションは特定できるため、入り口付近に全入居者のポストがあるようなビルやマンションであれば、ポストに会社名を記載しておけば、郵便物が届かないということはないでしょう。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
株式会社の役員の任期
2012/12/04相続登記について
2012/10/12相続と許認可を主に担当しております佐藤です。
不動産を相続する場合、相続登記は、何ヶ月以内に登記しなければいけないという期限はございませんので、亡くなられた方が所有されていた不動産を相続登記をせずに、所有者を亡くなられた方の名義のままにしておかれる場合がございます。
しかし、不動産を売りたいという時には、まず所有者を亡くなられた方から相続人の方へ相続登記をしてからでないと売ることができません。不動産の所有者の方が亡くなられてから相続登記をせずに何年か経った後、いざ相続登記をする時には、亡くなられた方の相続人であるお子様も亡くなられており、そのお孫様が相続人になる場合があります。そうなると相続人の数が増え、取得する戸籍も増えるので、その分費用も多くかかることになります。
また、相続人が多いと誰が相続するかということで遺産分割協議の話合いが、まとまりにくいという可能性もございますので、不動産の相続登記は、亡くなられてから、あまり時間を置かずにされた方がよいかと存じます。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい。
会社設立の注意点(6) 代表取締役の選任機関
2012/10/01商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
取締役会のある会社の場合、代表取締役を選ぶ機関は「取締役会」と定められていますが、取締役会のない会社の場合、下記の3つの方法があります。
1,定款
2,定款の定めに基づく取締役の互選
3,株主総会の決議
1番目の「定款」は、代表取締役の変更の度に定款を変更するというのは現実的ではないため、お勧めできません。
2番目の「定款の定めに基づく取締役の互選」は、取締役会のある会社と同様に、取締役全員で代表者を決めることになるので、一般的になじみ深いものかもしれません。
但し、出資者以外の方を取締役にされる場合、出資者の意思に反した方が代表取締役になるリスクがあります。また、変更登記の際には定めがあることを証明するため、議事録や就任承諾書以外に定款を添付する必要があります。
3番目の「株主総会の決議」は、取締役を定める機関である株主総会で代表取締役も定めるというものです。出資者の意思が反映されやすいため、株主が多いなどの事情がなければ、株主総会の決議で定める方法をお勧めしています。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
京都の建設業許可申請について
2012/08/27京都で建設業の新規許可・更新手続きをする場合の取扱いが平成22年7月1日以降より、従前は求められていなかった確認書類を求められることになりました。
専任技術者が、10年の実務経験ありとして、許可を取得する場合、実務経験期間中の在籍確認書類を提示する必要があります。
在籍確認として提示する書類としては、年金の被保険者記録照会回答票がありますが、年金の被保険者記録照会回答票だけで在籍の確認ができない場合は、その補完資料として日報、賃金台帳や、出勤簿等の提示を求められる場合があります。
尚、在籍確認は、個人事業主であった期間は、省略することができます。
また、経営業務の管理責任者や、専任技術者の常勤性確認として、住民票の他に、健康保険被保険者証などが必要なのですが、経営業務の管理責任者及び専任技術者が、実際会社に常勤していることが証明できなければなりませんので、保険者証に会社名の記載がない国民健康保険の保険証は、添付書類としては認められません。
国民健康保険の保険証しかない場合は、源泉徴収簿及び領収済通知書又は、出金簿及び賃金台帳が必要になります。
京都で建設業の許可を取得しようとする場合、平成22年7月1日以降より、提示する書類が増えて、許可申請が以前に比べて手間取るようになりました。
これから京都で許可を取得される予定の方は、在籍確認が証明できるような書類を作成しておくか、残しておいた方がよいかと思います。
役員変更登記について(1) 議事録の就任承諾書の省略が認められない場合
2012/08/23商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。
株式会社の役員変更登記において、選任された役員が株主総会もしくは取締役会に出席し、就任を承諾したことが議事録の記載により確認できる場合は、就任承諾書の添付を省略することができます。
これまで、「即時就任を承諾した」や「席上で就任を承諾した」などの記載が議事録にあれば、就任承諾書を省略することができましたが、「即時就任を承諾した」旨の記載では、総会に出席していることが明らかとはいえないので、就任承諾書を省略することができないとの取扱もあります。
なお、「即時就任を承諾した」旨の記載であっても、出席役員として記載されているなど、出席が明らかな場合は就任承諾書を省略することができます。
また、「席上で就任を承諾した」の記載がある場合は出席していることが明らかなので、就任承諾書を省略することができます。
今後、総会の中で就任承諾をされた場合は、議事録の記載は「席上で就任を承諾した」に統一された方がよいかと存じます。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
法人化のミニセミナー(勉強会)
2012/08/07代表の谷口です。
当事務所が、日頃からホームページなどでお世話になっている有限会社リウムさん主催のミニセミナー(勉強会)で、「あなたにぴったりの起業形態」と題して、お話しさせて頂く機会を頂きました。
私が、法人化を検討されている方に、お伝えしたかったことは主に3つでした。
1,法人化は手段であって目的ではない
実現したい事業・目標・夢によって、最適な法人形態は変わってくるので、まずは事業計画を考えて頂きたい。
2,最低限の法律知識は必要
法人化するとなると色々な専門用語が出てきます。
きちんとした知識がなく、あいまいなまま事業を始めてしまうと、思わぬ落とし穴に落ちることあるので、ある程度は法律・会計に関することも知って頂きたい。
3,法人化はメリットばかりではない
法人化すると色々な金銭的・事務的負担が増えるので、法人化するメリットとデメリットを天秤にかけて本当に法人化がメリットがあるのかを考えて頂きたい。
法人化を検討されている方は、法人化が本当に必要か、検討してみて下さい。
会社設立・法人設立については、こちらをご覧下さい。
建設業法施行規則と建設業法第27条の23第3項の一部改正
2012/08/07建設業法施行規則の一部と建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部が改正されました。改正内容は、下記のとおりです。
① 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(平成24年7月1日施行)※経営事項審査の際、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に未加入の場合、それぞれ40点の減点(雇用保険、厚生年金保険及び健康保険全てに未加入の場合120点の減点)
② 建設業の許可申請及び許可更新時の添付書類として、保険の加入状況を記載した書面の提出(平成24年11月1日施行)
③ 施行体制台帳に、保険加入状況を記載(平成24年11月1日施行)
※施行体制台帳とは、特定建設業者が、工事を元請で請負った場合で、下請契約の請負代金の額が3,000万円以上になるときは、下請負人の商号又は名称、建設工事の内容及び工期等を記載し、工事現場ごとに備え置く必要のあるものです。
上記の改正により、建設業の許可を申請する際には、保険加入状況を記載した書面を求められることになり、もし、未加入だった場合は、許可を行うと同時に保険に入るよう文書にて指導されます。そして、指導後尚未加入の場合は、保険担当部局(健康保険、年金なら年金事務所、雇用保険なら地方労働局)に通報されることになります。
この改正に至る背景には、これまで建設業界では、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を負担しない保険未加入企業の存在があり、法律を守り、適正に法定福利費を負担する企業が、保険未加入企業と比べて、競争上不利になったり、又、保険未加入だと、公的保障が受けられない為、保険未加入が、建設業界の就職人数減少の一因となっていました。
そこで、これら是正の為、社会保険未加入問題に対し、上記改正内容の対策が取られました。
今回の改正で対象になるのは、保険に入る必要があるのに、未加入の会社の場合であり、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険等保険の適用除外で、今まで入っていなかった方は、今まで通り入る必要はこざいません。
建設業については、こちらをご覧下さい。

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740