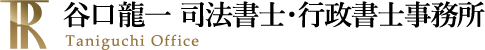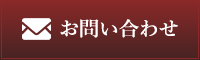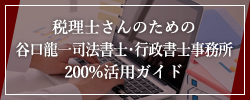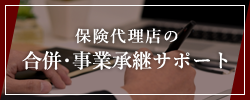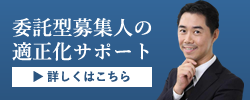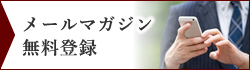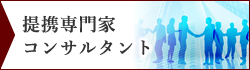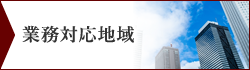- ホーム
- コラム
コラム
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
監査役の会計監査限定の登記が必要になりました
2015/06/29商業登記を主に担当している出口です。
平成27年5月1日、会社法の改正があり、監査役の会計監査限定の登記が必要になりました。下記に該当する場合は登記が必要になりますのでご注意ください。
定款に「監査役の権限を会計監査に限定する」旨の文言が入っている
平成18年5月1日の会社法施行時に小会社(資本金が1億円以下で、負債総額が200億円未満の会社)で、かつ、全ての株式につき譲渡制限がある会社
(監査役会、会計監査人設置会社を除く)
なお、この登記は平成27年5月1日以降で、最初に監査役に関する変更登記を行うときに併せて行えばよいことになっており、併せて行う場合は登録免許税は別途かかりません。
住宅ローン完済後の担保抹消はお早めに!
2015/04/28不動産登記を主に担当している山添です。
住宅ローンを完済されても、土地や建物に設定されていた担保は、法務局への抹消登記手続きをしなければが抹消されないのはご存知でしょうか。
住宅ローン完済後、金融機関より書類の返却を受けます。
その書類の中には担保抹消登記の重要書類が含まれています。
有効期限がある書類もあり、しばらく放置しておくだけでいつのまにか期限が切れ、再発行の手続きになり、余計な費用がかかってしまうこともあります。
最も面倒なのは数年放置して書類そのものを紛失してしまう場合です。
こうなると、金融機関に再度書類を発行して頂く必要があり、時間や手間がかかってしまいます。
住宅ローンを返済され、金融機関から抹消書類を受け取られた場合は、お早めに登記手続きをされることをおすすめいたします。
役員の死亡による退任登記をお忘れなく
2015/04/28商業登記を主に担当している出口です。
当事務所では役員変更登記をよくご依頼頂くのですが、下記のようなやりとりを何度かさせて頂いたことがあります。
お客様「役員は全員再任でお願いします。」
出口「かしこまりました。(登記簿を見ながら)取締役A、B、C、Dが再任ですね。」
お客様「あ、Aはもう数年前に亡くなっています。」
意外に思われるかもしれませんが、死亡による退任登記がされていないことがときどきあります。代表者はその方が亡くなられた事は知っているのですが、役員として入っている、あるいは退任登記をしないといけないという意識が無いようです。
例えば、代替わりをして代表取締役は子に変更しているが、平取締役として親が残っていて亡くなられた場合など、役員として名前は残っているけれども、実際はほとんど業務に携わっていない方である場合が多いです。
取締役、監査役が亡くなられた場合は、死亡から2週間以内に退任登記をする必要がございます。登記が遅れれば、過料(罰金)がかかってくることがございますので、お早めにお手続きされることをおすすめ致します。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表取締役変更の決議ができない場合
2015/04/23商業登記を主に担当している出口です。
4月1日から新代表者に代わるというのはよくある事かと思います。ではそれが決まるのはいつ頃でしょうか。通常、数ヶ月前には会社内部で決まっているのではないでしょうか。但し、実際に新代表者に就任するには、当然選任決議が必要です。
就任日より前に代表取締役の予選決議を行う場合で、決議機関が「取締役会」や「取締役の互選」の場合、有効に決議を行うには条件があります。それは、取締役全員に変動がなく、かつ、就任前一ヶ月以内程度であることです。
つまり、下記のような場合は予選ができません。
2月の取締役会で4月1日からの新代表取締役を予選する
→ 一ヶ月以上前なので不可
3月31日時点で現代表取締役が役員を退き、4月1日から新代表取締役が就任する
→ 予選決議のときから取締役が減っているから不可
予選決議の後、新代表取締役の就任前に新しい平取締役が就任した
→ 予選決議のときから取締役が増えているから不可
就任日より前に選任決議をされる場合はご注意ください。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
若年技術者の雇用による経営事項審査の点数アップ
2015/03/13建設業を担当しています大掛です。
平成27年4月1日から経審の審査項目に新しい項目が追加されます。
その1つが若年技術者の雇用状況を評価する項目で、具体的には
・技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が名簿全体の15%以上
・審査基準日から1年以内に新規雇用した35歳未満の技術職員が名簿全体の1%以上
の基準を満たせばそれぞれ一律1点が加点されます。
経審の点数アップをお考えの経営者の皆様、新規雇用をされる際にはこの点も考慮されてはいかがでしょうか?
※技術職員名簿に記載されている技術者とは
1、2級の国家資格を持っているか、10年以上の実務経験がある技術者のことです。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
長期間登記をしないと知らない間に会社が強制的に解散になることも
2014/11/21商業登記を主に担当している出口です。
平成26年11月17日、全国の法務局から休眠会社・休眠一般法人へ通知が送られました。
休眠会社・・・12年間登記をしていない株式会社
休眠一般法人・・・5年間登記をしていない一般社団法人及び一般財団法人
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や会社の印鑑証明書の交付を受けていたとしても関係無く、最後に登記をしてからの年数によります。
平成27年1月19日までに登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、自動的に会社が解散したとの登記がされてしまいます。
何らかの事情で法務局からの通知が届かなかったとしても、官報による公告がされているため、効力が発生します。長期間登記をした覚えのない方は、この機会に一度確認されてはいかがでしょうか。
詳しくは法務省の「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
株式会社設立の登録免許税が半額に!!
2014/09/16代表の谷口です。
当事務所は京都商工会議所の登録専門家ですので、これから株式会社設立をお考えの方は、是非、ご相談ください。
詳しくは京都市のHPをご覧ください。
京都商工会議所・がんばる経営応援専門家 こちら
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
役員報酬をなしにしたら建設業許可の更新ができないかも
2014/09/08代表の谷口です。
下記のような事例で役員報酬をなしにしてしまうと、常勤性の確認ができず、最悪の場合、更新ができないこともありえます。
税理士さんや社会保険労務士さんは、役員報酬についてご相談を受けることの多いと思いますので、ご注意ください。
A社の代表取締役・経営業務の管理責任者・専任技術者はBさんで、建築一式の建設業許可を4年前に取得しました。
Bさんの息子のCさんは他社で修行していましたが、3年前よりA社に勤務し取締役となりました。
代替わりをしようということで、Bさんは代表取締役から取締役に、Cさんは取締役から代表取締役に変更すると同時にCさんは毎日出勤するものの、役員報酬はなしにしようという手続きを考えています。
建設業許可では、経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤でなければなりません。
そして、新規申請や更新の際には常勤性の確認があります。
常勤性の確認は健康保険証・住民税特別徴収税額通知書等で行われます。
上記の事例では役員報酬をなしにすることにより、社会保険から外れることなり、常勤性の確認できる健康保険証等が提出できないことになります。
他の書類でも常勤性の確認ができないとなると、常勤性の要件を確認することが難しくなり、許可の更新ができなくなってしまうおそれがあります。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
建設業許可の更新時期は自分で管理を
2014/07/30代表の谷口です。
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
自動車免許の更新のように、建設業許可の更新については行政から更新の連絡は来ません。
たまに行政が更新時期を教えてくれなかったといって、怒られる方がいらっしゃいますが、更新時期の管理はあくまでご自身でしなければなりません。
また、京都府では建設業許可の更新手続きをする場合の取扱いが平成22年7月1日以降より、従前は求められていなかった確認書類を求められることになり、手続が煩雑になりました。
書類の準備が間に合わないと、最悪のケースでは更新手続きが間に合わず許可が切れてしまい、新たに許可が下りるまで仕事を受注できないということもあり得ます。
ですから、更新時期をきちんと管理し、早くから更新の準備をされた方がよいでしょう。
当事務所では、更新の3−4ヶ月前程度から準備されることをお勧めしております。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
未登記の建物・家屋の相続による名義変更はどうすればいい?
2014/02/09代表の谷口です。
法律上、建物を建築した場合、表示登記をすることが義務づけられており、怠ると罰則もあります。
しかしながら、建物の登記をされていないこともあります。
相続のご相談・ご依頼のときに、遺産を調査していく中で建物の登記がされていないことが分かる場合があります。
表示登記と権利登記
まず、建物の登記といっても、表示登記と権利登記の2つの登記があります。
表示登記には、建物の所在や面積、構造、建物の種類などが記載されています。
権利登記は、表示登記の後に所有者がだれか、担保に入っているかということが記載されています。
(なお、表示登記にも所有者の記載はありますが、権利登記の所有者と法的な効力が異なります)
名義変更をどうするか
相続手続の中で、未登記の建物があった場合、いくつかの手続が考えられます。
1,遺産分割協議、表示・権利登記をきちんとして、名義をはっきりさせる
2,遺産分割協議と表示登記だけをして、権利登記はしない
3,遺産分割協議だけをする
1が名義に関してのトラブルのおそれが一番少なく、2,3の順に名義に関してのトラブルのおそれが多くなります。
名義に関してのトラブルとは、下記のケースが考えられます。
・20年、30年と長期間経過して、当時のことを知らない世代だけになった場合、遺産分割協議も紛失してしまっていると、相続人間で誰が相続したのかがわかない。
・建物を売却しようとするときに買主への名義変更が出来ないので、売却できない。あるいは売却の際に表示・保存登記をしなければならず、時間が経過しており、登記をするのに手間・費用がかかる。
・リフォームや事業のために借入をするために、建物を担保に入れようとしても、登記がないので担保に入れることが出来ないため、借入が出来ない。
・敷地が借地の場合、地主が土地を売却したときに新たな地主に借地権を主張することが出来ない。
後日のトラブルになってから手続をすると最初から手続をするより、より時間や費用がかかるので、最初からきちんと登記をされることをお勧めします。
なお、表示登記に関しては、土地家屋調査士さんの分野となりますが、当事務所では提携している土地家屋調査士さんがいますので、一括して手続を進められます。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい

- こんな悩みあるんだけど・・・
- ウチの場合どうなるんだろう・・・
- お願いするかどうかわからないけど・・・
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
 TEL 075-354-3740
TEL 075-354-3740